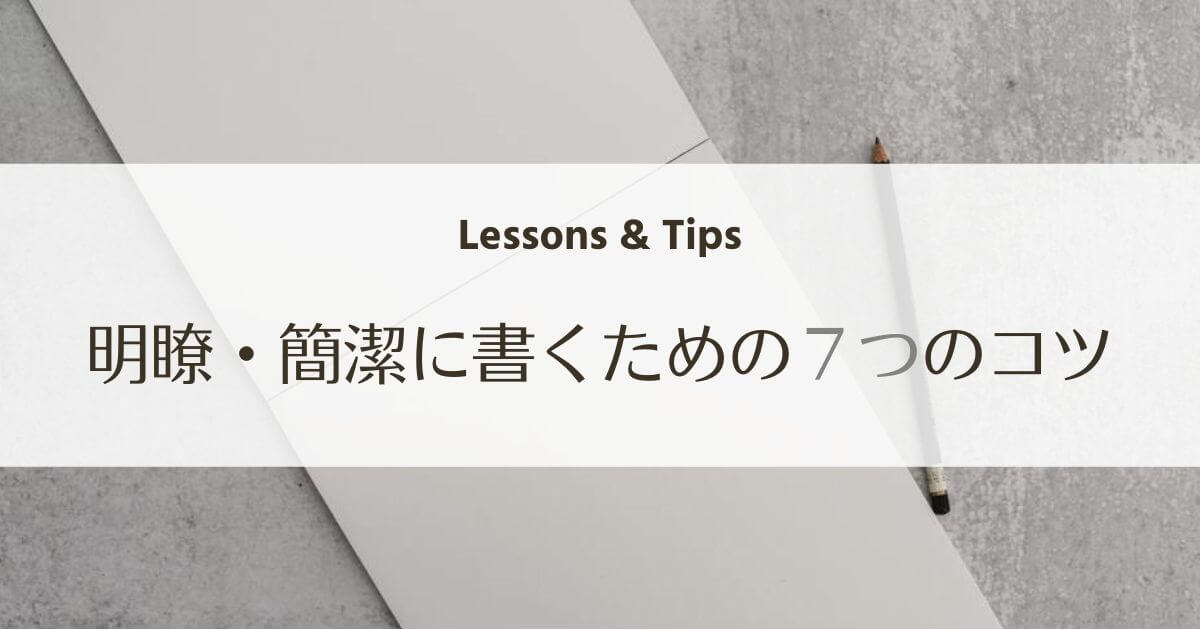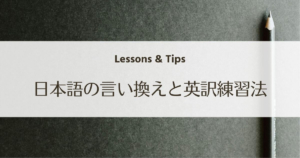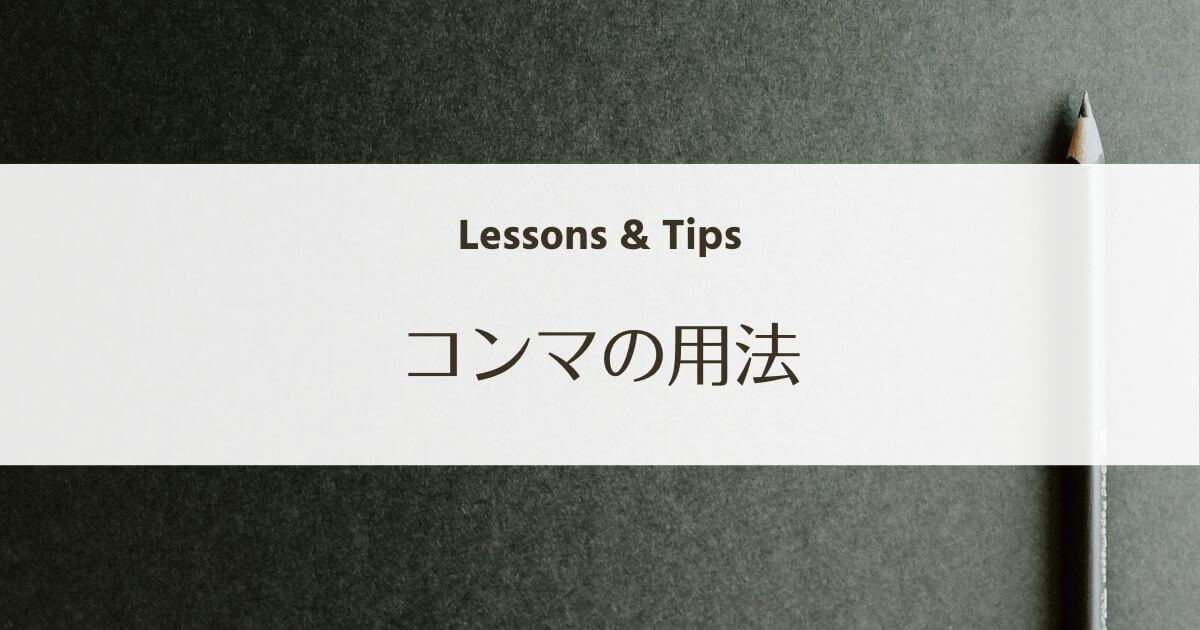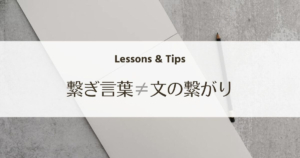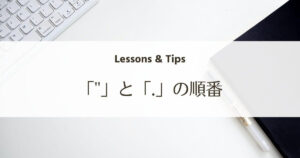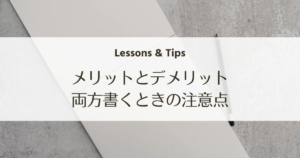英語で文章は書けるけれど、「どうしても文章が長くなりがち」「もっとスパッと端的に書けるようになりたい!」という悩みがある方は多いのではないでしょうか?・・・私がまさにそれです。笑
分かりやすいクリアな文章を書くためには、アカデミックライティングを意識するといいですよ。^^
ビジネスやアカデミックの現場で文章を書く必要がある人にとっては特に重要です。回りくどいダラダラとした文章では、「伝えたいこと」「説得したいこと」が伝わり辛く、文章の目的が果たせないからです。
今回は、明瞭簡潔に書くための7つのポイントをご紹介します。簡潔でクリアな文章を書くコツを学びましょう。
アカデミックライティングとは
レポートや論文などのフォーマルなライティングはアカデミックライティング(academic writing)といい、特有のスタイルやルールがあります。
日本語でも、カジュアルなメールやチャットの文章と大学や会社に提出する報告書では文体や使用する語彙が違いますよね。同様に、英語でも場面によってふさわしい言語(スタイル)は異なります。
アカデミックライティングでは以下の3点が重要ですが、今回はその中でも②の文体にフォーカスします。
- フォーマルな語彙を使う
- 簡潔かつ明瞭に書く
- 論理的に書く
アカデミックライティングにふさわしい文章とは?
ビジネスやアカデミックの現場で書く文章では、明瞭さ(Clearness)・簡潔さ(Conciseness)が命です。
このような現場で作る文章の目的は、「読者に事実や筆者の考えを理解してもらうこと」ですよね。
読者には内容にフォーカスしてもらいたいため、文章を読むこと自体にストレスを感じさせないようにするのが重要です。途中で立ち止まったり戻ったりしなくても文章の内容がスッと入ってくるような、ストレスフリーな文章が理想です。
そのためには、難解な言葉や複雑な構文は使わず、とにかくシンプルで分かりやすい文章にするのが大事です。
- 一文に要点はひとつにする
- 文章は短くする
- 余計なこと、無くても困らないものは書かない
- 同じことを何度も繰り返さない
知識があり長い文章が書けてしまう中上級者ほど、短い文章を書くことが苦手だと思います。
短い文章は稚拙と思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。簡潔にスパッと表現できている文章の方が圧倒的に読者フレンドリーで好まれますよ。
もちろん長文にならざるを得ない時はあります。大事なのはあくまでバランスです。ただ、意識しないとどうしても長くなってしまいがちです。とにかく「短く簡潔に」を意識しましょう。

私も文章が長くクドい自覚があるので、とにかく常に「短く」を心がけています。(それでも長いと校正者に指摘されるんですけどね。笑)
では、簡潔に書くための具体的な方法を見ていきましょう。
英語の文章を簡潔に書くための7つのコツ
1.同じ意味なら、短い表現を使う
英語には同じ意味を表す複数の表現がありますよね。長い表現の方が畏まって見えるとか、フォーマルな感じがするとか、そんなことはありません。
同義の表現が複数ある場合は、短い方の表現を選びましょう。
普段のライティングではもちろん同義なら好きな方を使えばよいですが、アカデミックライティングにおいてはシンプルさは命です(笑。短い表現を使いましょう。
Participants provided consent prior to participating in the survey.
⇒Participants provided consent before participating in the survey.
We made students take this test in order to assess their comprehensibility.
⇒We made students take this test to assess their comprehensibility.
In the event that an adverse event occurs, the treatment should be discontinued immediately.
⇒If an adverse occurs, the treatment should be discontinued immediately.
- in order to ⇒ to
- so that S can ⇒ to
- be able to ⇒ can
- prior to ⇒ before
- for the purpose of ⇒ to
- due to the fact that ⇒ because
- on the grounds of ⇒ because
- despite the fact that ⇒ although
- with regard to ⇒ about
- in the event that ⇒ if
- 注意:いつもこの通りに書き換えられるとは限りません。文脈に応じて判断してください。
2.受動態ではなく能動態で書く
受動態は「be動詞」を用いるため動詞のインパクトが弱く、動作主も分かり辛いです。また、文章が長くなりがちです。
能動態にした方がスッキリとダイレクトに書けることが多いため、能動態で書くようにしましょう。
受動態は避け、出来る限り能動態で書きましょう。
This survey was conducted by ABC Inc. in 2020.
⇒ABC Inc. conducted this survey in 2020.
Internet literacy was required to participate in this survey.
⇒This survey required participants to have Internet literacy.
These data were analyzed to examine the relationship between A and B.
⇒We analyzed these data to examine the relationship between A and B.
英語論文の校正者からよく聞く話なのですが、日本人は受動態の文章が特に多いようです。日本語では主語をよく省略するため受動態の文章は書きやすいのかもしれませんね。
能動態で書ける内容でも、無意識のうちに「受動態」を選択している場合があるかもしれません。



ついつい受動態で書いてしまった場合は、能動態で書けないか視点を変えて考えてみましょう。
視点を変えて無生物主語にするとスッキリ書けることも多いですよ。視点・発想の転換については以下で説明していますので、良ければ併せてご覧ください。
3.Be動詞は使わない
受動態を避けたい理由と同じですが、「be動詞」を使うと動詞のインパクトが落ち、文章も長くなりがちです。
実際には完全に排除することはできないと思いますが、極力使用は避けましょう。もっとダイレクトな「Active verb」で表現できないかを考えます。
Be動詞は極力避ける。
「be動詞」を使う表現のため、「There is/are ~ 構文」や、「It is xxx to/that ~ 構文」も避けます。
この構文を使わなくてももっと短い語数で同じ意味を表現できますし、その方が文章としても明瞭・簡潔だからです。
There were three treatment groups in this study.
⇒This study had three treatment groups.
It is necessary that researchers obtain informed consent from participants.
⇒Researchers must obtain informed consent from participants.
<ちなみに>
留学中、私のチューターはこの「be動詞」の使用に鬼厳しくて、一切使用させてもらえませんでした。当時は、「受動態とか文法的に使わなきゃいけないんだからゼロとか無理でしょ!」と心の中で叫んでいたのですが、彼女はどんな文章も「be動詞」を使わない文に直してくれたんです(見事としか言えません)。
その鬼トレのお陰で、「be動詞」を使おうとする度に他に方法はないか考えるようになりました(当時は)。結果的にものすごくいいトレーニングだったんだなと、今では感謝しています。
これは極端な例で、実際には文章量が多くなれば完全に排除することは不可能ですし、する必要もありません。ただ、それくらい意識しないと結構無意識に使ってしまうものです。ご興味ある方はトレーニングの一環として是非お試しください ^^
4.Strong verbを使う
一語で表現できる動詞(=単体動詞、single verb)はインパクトが強く、アカデミックライティングではこうした strong verb の使用が好まれます。
Strong verb を使う。
逆に一語で表現していない動詞というのは、bring about (= cause)などの句動詞のほか、名詞や副詞を伴った表現を指します。例えば次の太字(黒)のようなものです。
We made a decision to accept the offer.
⇒We decided to accept the offer.
The next chapter will provide an explanation for the theory.
⇒The next chapter will explain the theory.
We need to take into consideration the client’s satisfaction.
⇒We need to consider the client’s satisfaction.
いずれも修正前の文章では「名詞化」された動詞を使用しています。名詞の部分(decision, explanation, consideration)に本来の動詞の意味があるので、make, provide, take などには意味がありません。
「実質的に意味が無い語」は外しましょう。名詞化されている部分を本来の動詞形に戻すことで不要な語が取り除かれ、語数も減りスッキリします。
なお、名詞や副詞の意味を汲み、別の動詞で表現できる場合もあります。
This exercise has a positive effect on neck pain.
⇒This exercise reduces/alleviates neck pain.
These behaviors negatively affect the treatment’s prognosis.
⇒These behaviors worsen the treatment’s prognosis.
このパターンは少し考えないと思いつかない場合もあるので、ライティングの時に意識するというよりは編集の際に修正できないか考えてみるのがいいと思います。
結局、語数が少ない方が簡潔で良いということですね。
5.名詞化を避ける
4では動詞の名詞化について触れましたが、形容詞の名詞化もあります。いずれにせよ、名詞化は冗長な表現であることが多いため避けましょう。
名詞化を避ける。
動詞の場合と同様、形容詞から派生した名詞を使ってはいけないという訳ではありませんが、もとの形容詞を用いた方がシンプルに表現できるかもしれません。
例は無限にありますが、例えば下記などが一例です。
- effectiveness ⇒ effective
- worthiness ⇒ worthy
- relevance ⇒ relevant
- appropriateness ⇒ appropriate
- validity ⇒ valid
6.否定文ではなく、肯定文で書けないか考える
否定文よりも肯定文にした方がストレートに伝わる場合があります。
否定文ではなく、肯定文で書く。
アカデミックな文章では否定文が好ましくないなどということはありません。否定文を書くこと自体に何の問題もありません。
ただ、少し見方を変えれば肯定文で表現できる場合や、肯定文にした方が明瞭簡潔に表現できる場合があるのは事実です。
He did not agree to take this medication.
⇒He disagreed/declined to take this medication.
The trends were not different between the two studies.
⇒The trends were similar between the two studies.
This study did not show any positive effects of this exercise.
⇒This study failed to show any positive effects of this exercise.
In this chapter, we do not use technical terms so as not to cause any confusion.
⇒In this chapter, we use simple words to avoid any confusion.
否定文⇔肯定文の変換は、「思いつくかどうか」という問題もあると思います。ライティングの際に意識するというよりは、編集の際に肯定文に修正できないか考えてみるのがおすすめですよ。
7.不必要な数量詞・修飾語は外す
分かりやすく簡潔な文章にするためには、「無くても困らない(意味が変わらない)ものは削除する」というのが鉄則です。
不必要な数量詞・修飾語は入れない。
そのため、強調やニュアンスを表す以下のような表現は、削除できる場合がほとんどです。
so, just, quite, really, very, actually, definitely, kind of, type of, …etc.
口語やメール・チャットでは、こういう語の使用が癖になっている人もいるのではないでしょうか?
微妙なニュアンスを出すために色々と副詞を付けたくなってしまう気持ちはよく分かります。
でも、文意を変える役割を担っていないのであれば、その修飾語は要らないものだと考えましょう。必要最低限のもので表現するのがポイントです。
このほかの修飾語についても同じルールで考えます。全体の語数は出来るだけ減らしましょう。
修飾語ではありませんが、文頭に Also, Therefore, Moreover… などやたらと「つなぎ言葉」を置くのもよくありません。この点については「英作文でつなぎ言葉を使う前に考えたいコト」で説明していますので、気になる方はチェックしてみてください。
文章は出来るだけ短くする
ここまでも繰り返し強調してきましたが、読みやすい英文にするには「文章を短くする」ことが大事です。
上で紹介したコツは全て「単文」レベルの話ですが、もちろん、必要以上に複文・重文を使わないことも大事です(節を繋げると、全体として文章が長くなってしまいますからね)。



私は特に and などで節を繋げて複文にしてしまう癖があるため、気を付けています。
- 切れるときは切る
- 節ではなく、名詞句などでコンパクトに情報を付加できないか考える
などに意識するといいですよ。
付帯状況の with なんかも、上手く使えると文章の簡略化に役立ちます。下記で例文をたくさん載せていますので、良ければご参考ください。
コロンやダッシュは厳密には文を切っていることにはなりませんが、ダラダラと文章で書くよりも、リスト化などを用いた方がスッキリとして読みやすくなるかもしれません。句読点は上手に使えるようになると楽ですよ。もし使い方に自信が無い方は、下記でご確認ください。
もっと勉強したい方へ
海外の大学の学生向けライティング情報
英語のサイトですが、本稿で紹介したようなアカデミックライティングのポイントを例文を交えて説明してくれています。
オンライン講座
もっと勉強したい方はオンライン講座もおすすめです。
アカデミックライティングの講義はたくさんありますが、これまで受講した中で一番良かったのは「edX」で提供されている「Academic Writing Made Easy」です。聴講(audit)であれば無料で視聴できますよ。
【基本情報】
提供元:Technische Universität München (TUM)
言語:英語(基本的に原稿の読み上げで丁寧に話してくれるので、聞き取りは容易)
費用:聴講なら無料
簡潔に文章を書くためのコツやパラグラフ構成のポイントなど、アカデミックライティングの基礎が効率よく学べます。今回の内容に関連するユニットは Unit 4 なので、ここだけ見てみるというのもおすすめですよ。
Scientific Paper を書く人であれば、もっと詳しく学べる公開講座もあります(英語・無料)。以下で紹介していますので是非チェックしてみてください。
AI 英文チェックツール
文章には人それぞれ癖も出ますし、コツを学んだからといって一朝一夕で簡潔な英文が書けるようになる訳ではありません。自分では気づかないことも初めはたくさんあると思います。
Conciseness という観点で英文チェックをしてくれる AI ツールも今はたくさんありますので、ライティングの頻度が高い人は是非使ってみてください。文章の質・読みやすさがアップしますよ。
信頼性・精度から考えると、Grammarly がおすすめです。


まとめ
短く簡潔に書くために心がけるべき7つのポイントをご紹介しました。
- 同じ意味なら、短い表現を使う
- 受動態ではなく能動態で書く
- Be動詞は使わない
- Strong verbを使う
- 名詞化を避ける
- 否定文ではなく、肯定文で書けないか考える
- 不必要な数量詞・修飾語は外す
明日からすぐには変えられないかもしれませんが、何事もまず意識することから始まります。是非、出来そうなところからトライしていきましょう^^